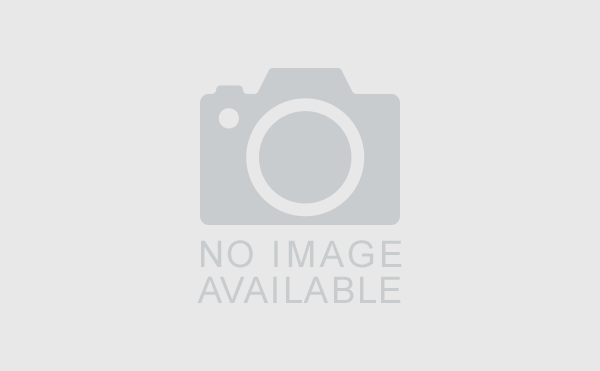大学・大学入試情報
映画評論家のSNS投稿「偏差値35で学術会議担当?」炎上から大学のあり方を考える

炎上という言い方はすっかりSNS用語になってしまった。
10月下旬、映画評論家がXで「偏差値35で学術会議担当?」と発信したことで、彼に多くの批判が寄せられた。もともとは東京大教授のX投稿「「法人化で独立性高める」と強調 学術会議総会で小野田紀美担当相 石破政権時代と同じ、自民党政権の公式見解を繰り返す儀礼的なスピーチだった」へのコメント付きリツイートである。
これに対して大学に関わる2人の識者がSNSで発信している。
千葉商科大学准教授の常見陽平さんはSNSでこう訴えた。
「偏差値で政治家を語るのは、議論の放棄であり、知性の放棄である。知性と品性を鍛え、議論の質を高めよう。そして、一般論として学歴差別発言は、自らの知性、品性が乏しく、学歴無意味論を援護してしまうという構造も忘れてはならない。レベルの低い高市、小野田批判が、むしろ彼女たちの応援団になっている構造とも似ている。皮肉なことに」(11月5日)
大学ジャーナリストの石渡嶺司さんは次のようにクギをさす。
「学歴と政治家の見識は関係ありません。高校卒業後の職歴などで政治家としての能力を高めているのであれば、偏差値は無関係です。主義・主張が違うのであればその点を批判すればいいだけです」(11月5日)
今回の「偏差値35」炎上は、偏差値とは何かを考えさせる機会を作ってくれた。
そもそも、から偏差値のあり方を考えてみよう。
大学で学ぶだけの力を学生は持っているのか。大学が入学試験で受験生に一定の学力を求めるのは、入学後の勉強へ取り組む力を測るためである。受験生はその学力を身につけるために勉強に励む。
ここで大学と受験生のマッチングが行われる。
その大学に入学できるかを測るものさしが入試難易度である。これは偏差値と言いかえることができる。
偏差値は、受験生が大学を選ぶ際の目安の一つである。大学に入るための到達目標といっていい。偏差値のベースとなるのは、受験生一人ひとりが抱えている予備校の模擬試験での成績だ。大学受験では成績の高い生徒から合格する。それゆえ生徒の偏差値が下がるにつれ合格者は減り、不合格者が増える。合格者と不合格者が同数になるあたりが、その大学の偏差値となる。
これは「合格確実ライン」ではなく「合否の分かれ目ライン」といったほうがわかりやすい。
偏差値は母集団ごとに算出される。
したがって、偏差値を生み出す校内テストや予備校の模試など、異なる試験で算出される偏差値を同じように使うことはできない。
また、入試科目数の少ない大学にはその科目が得意な受験生が集まり偏差値は高くなりがちであり、同じ模試の偏差値で科目数が異なる大学を比べられない。
偏差値を「合否の分かれ目ライン」と考えるとしっくりくる。
「偏差値35」の場合、合格者は「偏差値35以上」の受験生であり、当然、偏差値がそれよりももっと高い人も含まれる。偏差値が50の人が第1、第2志望校に受からず、「偏差値35」の大学に入学するケースもあるわけだ。すべての学生が「偏差値35」ではない。
「偏差値35」の学生がいるのも確かだ。実際、基礎学力が不十分で中学生からやり直さなければならない学生もいる。いくつかの大学はそれも十分承知の上で、こうした学生に対して学習支援を行っている。その結果、大化けして学力が十分備わり、本来の大学教育のおかげで専門知識と教養が身につく。それを社会が評価して企業に就職できる。資格試験合格にもつながり専門性が高い仕事に従事できる。
常見さん、石渡さんは「偏差値35で学術会議担当?」という視点について、学歴差別発言であり、政治家の資質と関係ない、と訴える。まったく同感である。
わたしはさらに「偏差値35」に限定されずそれ以上の学生がおり多様化している、と付言しておきたい。極論すれば、偏差値ではおさまりきれない、さまざまな能力を持った学生がいる。そういうキャンパスがあってもいいではないか。
もちろん、「偏差値35」の学生をネガティブに捉えるわけではない。偏差値で測れないポテンシャルを持っているかもしれない、そんな彼らこそ政治家になってほしい、と思っている。
政治家の資質を測るのは偏差値ではない。優れた政策立案能力と厳しい責任感、相手を傷つけない適切な言葉を駆使できる発信力、誰からも信頼を得られる倫理感を持ち合わせているかどうかである。これらを十分まっとうするために「偏差値35」は関係ない。
それゆえ、「偏差値35で学術会議担当?」が炎上したのは、政治家を見きわめる上で偏差値を持ち出すことに大きな反発があった、つまり、学歴差別に対する拒否感がいっきに吹き出したという意味ではきわめて健全である。
逆説的なことをいえば、「偏差値35」の政治家が活躍すれば、出身校である大学は評価される。その大学にとってありがたい話だ。
「偏差値35」と名指しされた大学では、2025年度入学式に学長がこんな告辞をしている。
「世の中に目を向けると正解の無い社会課題がたくさんあります。たとえ、答え(正解)にたどり着けなくとも、答えを得ようと「もがく」プロセスを経験することは大きな成長につながります。教員は皆さんと同じ方向を向き、皆さんに伴走しながら皆さんの成長のために力を尽くしたいと思っています。遠慮することなく、授業の内容についてはもちろん、湧いてくる疑問の数々を教員にぶつけ、アドバイスを求めてほしいと思います」(大学ウェブサイト)。
政治家の仕事は「正解の無い社会課題」を解決することである。
教育ジャーナリスト 小林哲夫:1960年神奈川県生まれ。教育ジャーナリスト、編集者。朝日新聞出版「大学ランキング」編集者(1994年~)、通信社出版局の契約社員を経て、1985年からフリーランスの記者、編集者。著書に『女子学生はどう闘ってきたのか』(サイゾー2020年)・『学校制服とは何か』(朝日新聞出版2020年)・『大学とオリンピック』(中央公論新社2020年)・『最新学校マップ』(河出書房新社2013年)・『高校紛争1969-1970 「闘争」の証言と歴史』(中公新書2012年)・『東大合格高校盛衰史』(光文社新書2009年)・『飛び入学』(日本経済新聞出版1999年)など。