大学・大学入試情報
2026年度国公立大学理工系の「女子枠」は、38大学49学部で実施。共通テストは49万1272人が出願、対前年6704人増。「学士+修士」5年間の一貫教育で世界標準を目指す。

国公立大の「総合型選抜」は過去最多
文科省は2025年9月30日、「2026年度国公立大学入学者選抜の概要」を公表した。それによれば、国立の81大学415学部、公立の98大学225学部が入学者選抜を実施する。
対前年では、国立は1学部増、公立は2学部増となり、また募集人員は、国立が9万6344人(対前年24人増)、公立が3万4469人(同216人増)、合計13万813人(同240人増)と国公立とも増加した。
年内から始まる「総合型選抜」は対前年で、国立は6大学44学部増、公立は30大学61学部増と、国公立ともに過去最多。募集人員は、国立が8051人、公立が2012人の計1万63人で、募集人員全体の7.7%となった。
「学校推薦型選抜」は対前年で、国立は2学部増、公立は3学部増。募集人員は、国立が1万3243人、公立が9739人の計2万2982人で、募集人員全体の17.6%を占める。ともかく、募集人員は一般選抜・総合型選抜・学校推薦型選抜とも、対前年で微増となった。
国公立「女子枠」設置は38大49学部
さらに、「2026年度入学者選抜の概要」では、「総合型選抜」の増加が最も注目されている。中でも、理工系学部の設置が多い国立大で総合型選抜による「女子枠」の導入傾向がみられ、新たに8大学・12学部が増えて全体で38大学49学部にのぼることがわかった。
2026年度新たに女子枠を設けるのは、岩手大(理工)、山形大(工・フレックスコース)、京都大(理、工)、大阪大(基礎工)、広島大(理、工、情報科)、愛媛大(工)、埼玉大(工)、公立小松大(生産システム科)の8大学11学部。すでに女子枠を設けている高知工科大は、システム工学群で新たに導入。
また、10月18日には、「女子枠」を導入して30年を超える名古屋工業大が、女子枠に「一定の効果がある」との検証結果を公表。導入前は0~2人だった女子が、2025年度は女子の割合が20%を超えたというのだ。
今「公立大」が注目され急増している
昨今、公立大が大小の規模を含めて注目を浴びている。2015年89校、在学生14万8766人だった公立大は、2025年103校、17万367人と年々増加、拡大している。要因は、「私立大の公立化」と「地方再生化」等のようだ。
最大規模は、2025年9月に森之宮キャンパスを開設した大阪公立大(2022年大阪府立大+市立大の統合)で、学部生と院生を合わせて1万6160人に及ぶ。現在、12学部・学域、15大学院研究科があり、多くの学問が学べる。続く2位は、東京都立大で9143人だ。
一方、小規模な公立大は特徴ある学部を揃え、人気を得ている場合が多い。福島県立会津大コンピュータ理工学部、三条市立大工学部の金属加工、福井県立大の恐竜学部など。
さらに、不振の私立大を公立化し、既存の工学部に加えて薬学部を新設した山陽小野田市立山口東京理科大は、毎年志願者を多く集め、高倍率大学として注目されている。
また、地元の若者の流出を防ぐために、公立大を新設するケースもある。例えば、地域政策学部、地域創生学部などが目立つ。
共通テスト出願者数は49万1272人
大学入試センターは2025年10月3日、「2026年度大学入学共通テスト」の受付最終日午後5時現在の出願状況を公表した。出願総数は49万1272人。対前年同時期の出願総数より6704人増加した。
出願総数の内訳は、高校等卒業見込者が41万6965人、高校卒業者等が7万4307人。対前年では、高校等卒業見込者が6131人減、高校卒業者等が1万2835人増。現役生が減った一方、既卒生(浪人)は増加した。
確定出願者数などの詳報は、12月上旬に発表される予定であり、これを見ないとデータの分析はできない。ともかく、初めてのWeb出願が、既卒者にとっては手軽な出願となり、増加したようだ。
なお、出願総数はWeb出願により出願内容の登録後、検定料などの支払いを完了した者の数を示している。
学士+修士「一貫教育」5年間で修了
文科省は10月18日、大学学部と大学院修士課程を5年で修了する一貫教育を制度化することを決めた。それによって、大学院修士課程履修者を増やし、国際的に活躍できる専門人材を育成する方針を示した。
現在の制度では、原則として学部4年、修士2年の6年間学ぶ必要がある。文科省はこれを5年間で修了する新制度を設ける。大学が「5年コース」の設置を申請し、中央教育審議会(中教審)の審査を経て文科相が認定することを想定する。
具体案について文科省は、(1)学部で通常通り4年間学び、修士を1年で修了する(2)学部段階で修士の単位を先取りし、修士を1年で修了する──のいずれかを大学が選択する。教育の質を確保するために、文科省が大学の計画を審査し認定する。
世界のスタンダードは「修士課程」履修
「学士+修士=5年間」導入の背景には、欧米に比較して低い修士号取得率を向上させる狙いがある。すでに、東京大は2027年秋に開設予定の文理融合型の新学部「カレッジ・オブ・デザイン」で、5年一貫教育を実施する計画を発表している。
文科省の2025年のまとめでは、人口100万人あたりの修士号取得者数は日本の602人に対し、英国6057人、米国2649人、ドイツ2430人と大きな開きがある。加えて、日本の修士課程の在学者を分野別にみると、人文・社会科学は15%にとどまり、自然科学が大半を占める。因みに、大学院への進学率は東京大72.6%、東京理科大56.4%など。
グローバル社会の中、修士が世界のスタンダード。国連職員の採用資格も修士履修が条件。しかし、今の日本では大学進学率が59%を超えても、その上の大学院まで行く者は少ない。企業が、大学院卒の待遇を変えることが必要だ。ともかく、日本人が世界で活躍するためにも、もう少し学んでほしい。
大学&教育ウォッチャー 本間 猛:
東京理科大学理学部数学科1964年3月卒(参考 昭和39年:東京オリンピック・新潟地震)。元(株)旺文社取締役。中学・高校雑誌編集長,テスト部長,関西支社長等を歴任。
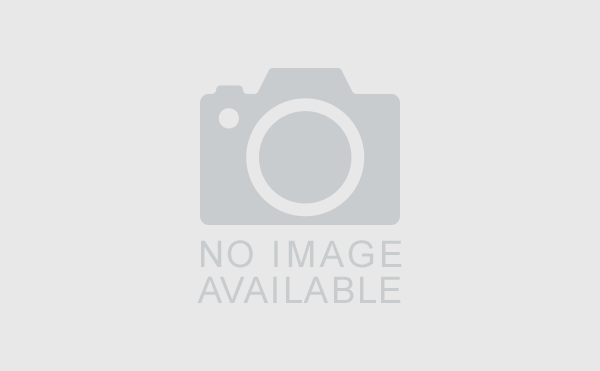
“” に対して1件のコメントがあります。