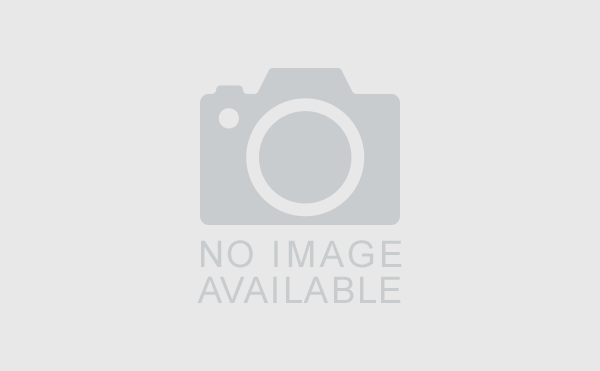第93回 大学・大学入試情報コラム
ネットで流される大学評価には気をつけてほしい
2025年5月
教育ジャーナリスト 小林哲夫
パソコンを起ち上げて最初の画面がニュースサイトという方は多いだろう。なかでも「Yahoo!ニュース」は群を抜いているのではないか。気になるニュースを知りたいときも、レストランや観光地情報を探りたいときでも、「Yahoo!ニュース」を見る方もかなりの数にのぼるだろう。
そして、「Yahoo!ニュース」の上位にあがった記事タイトルに目を見張り、思わずクリックしてしまう方も少なくないのでないか。このなかでは大学がらみの話が多く見られる。
いくつか紹介しよう。まずはA社の配信記事。
(1)「早慶上理の中で「進学したら最も自慢できそうだと思う大学」ランキング! 2位「早稲田大学」、1位は?」(2025年5月6日)
(2)「【男性が選ぶ】優秀な学生が多いと思う「GMARCHと関関同立の大学」ランキング! 第1位は「同志社大学」(2025年4月26日)
(3)「私立大学群「SMART」の中で最も知名度が高いと思う大学ランキング! 明治大学を抑えた1位は?」(2024年3月23日)
(4)「日東駒専の中で最も優秀な学生が多いと思う大学」ランキング! 2位「東洋大学」、1位は?」(2025年5月15日)
続いてB社の配信記事。
(5)「子どもを進学させたい「旧帝国大学」ランキング! 第1位は「京都大学」」(2025年4月19日)
(6)「【50代に聞いた】企業からの評価が高いと思う「電農名繊・四工大」ランキングTOP8! 第1位は「東京農工大学」(2025年5月13日)
(7)「【60代に聞いた】「関関同立・産近甲龍」の中で企業からの評価が高いと思う大学ランキング! 第1位は「同志社大学」」(2025年4月16日)
(8)「学生が楽しそうに見える「東京都の私立大学」ランキングTOP29! 第1位は「早稲田大学」(2025年4月16日)
ランキング1位を掲げるネット記事はよく読まれる。どんなテーマでも一番は気になるものだ。しかし、そのほとんどが人気投票である。1位の根拠として、たとえば論文数、研究費、国家試験合格者数、就職実績といったエビデンスに基づくものではほとんどない。それゆえ合理性にきわめて乏しい。「優秀」かのジャッジにおいて強いて言えば、予備校の偏差値を元にしている側面はある。だが、偏差値は大学単位ではじき出されるものではない。学部によってまちまちだ。
つまるところ、これらのランキングは感覚的な見方の寄せ集めでしかなく、信用するにあたっては注意深さが必要だ。
もちろん、「~~と思う」「~~に見える」という印象評価に基づくランキングにいちいち目くじらを立てることではない。だが、こうした評価が固定化され大学情報として受験生あるいは保護者が鵜呑みにしてしまうのは考えものだ。
上記の記事で気になる項目をいくつかとりあげてみよう。私見をまじえる
(3)「私立大学群「SMART」」とは、大学グループ分けの言葉としてまだなじみは薄い。Sは上智大(Sophia)で続いて明治大、青山学院大、立教大、東京理科大の頭文字をとったものだ。知名度の高さで1位になったのは青山学院大である。小学校受験、駅伝、ロケーション、おしゃれ感で名が知られているからだろうか。明治大からすれば、卒業生の政財界における活躍は青学を凌駕するので、不満はあろう。
(4)「日東駒専の中で最も優秀な学生が多い」1位は日本大となっている。数の論理で国家公務員、高校教員、警察官、消防官への就職、そして司法試験、弁理士、一級建築士など4校のなかで一歩も二歩もリードしている。少し前の大学トップの不祥事は学生とまったく関係がない話と言いたげだけの数字を持っている。もっとも東洋大にすれば、2025年度に入試制度改革を行って志願者数をいっきに増やして優秀な学生が集まっている、と言いたいところで、「日東駒専」のくくりはやめてほしい、と望んでいるだろう。
(6)「企業からの評価が高いと思う「電農名繊・四工大」」といっても受験生でさえどこの大学かよくわからない。まずは国立の工科系単科大学=電気通信大、東京農工大、名古屋工業大、京都工芸繊維大で、続いて都内の理工系がメインの私立大学=芝浦工業大、東京都市大、東京電機大、工学院大である。東京農工大が1位なのは同校出身に飛び抜けて優秀なエンジニアがいたことによるものか。8校のなかでもっとも多くのデジタル人材を送り出している電気通信大はもっと評価されてもいい。
(8)「学生が楽しそうに見える」1位の早稲田大は学校推薦型選抜、総合型選別での入学者が増えたことで、第1志望の学生が多いことと無関係ではないだろう。一般選抜の「入学者がほとんどだった時代、東京大を再受験する「仮面浪人」が少なからずおり、満足度が高いとは言い難かった。また、女子比率も高くなったことは大きい。2024年度は39.3%となり、4割目前だ。2020年代中には男女半々になるかもしれない。
ネット情報のこうした大学評価は、大学発行のパンフレット、メディアや受験産業が発行する大学情報誌よりも受験生に対する波及効果が高い。それゆえ、当事者である大学はたいそうナーバスになり、ネガティブ情報が出るとそれを打ち消すため躍起になることがある。
最近では「学歴YouTuber」を名乗る人たちが、SNSで独自の教育観から大学分析を行っている。女子大の大幅な定員割れ、大学の不祥事をおもしろおかしく語ることがあり、なかには参考になる情報がある。しかし、特定大学に「Fランク」とレッテルを貼り、根拠なく貶める語りも見られる。
ネット上で流される大学評価を鵜呑みにするのはきわめて危険だ。とくにX、インスタグラム、フェイスブックなど個人が伝える情報は要注意だ。発信する前に第三者(編集者)のチェックが入っておらず、まるで根拠がないデータ、思い込みやなかにはその大学に対する怨恨が示される場合があるからだ。こうなるとトイレの落書きと変わらない。
たとえば、ある人が、たまたま遭遇した学生、教員がとんでもないことをしでかして自分はおおいに迷惑を被った。彼らが所属する大学は最低だ、といった言説をSNSで蒔き散らかす。そんなものを信じてしまえば、大学のほんとうの姿から遠ざかるばかりだ。
また、こうした情報を受験関係者に触れ回すような「再生産」は、大学から名誉毀損で訴えられかねない。
これでは大学の良さを知る、大学のダメさを見きわめる―――いずれの機会も失ってしまう。
ネットがこれだけ普及しているいま、大学情報を読み解けるリテラシーは身につけておきたい。
ここで紹介した「~~と思う」「~~に見える」という印象評価の寄せ集めはまず疑ってかかっていい。とくに40代以上の人からの大学評価は、20年前、自分たちが学生だったころの大学観に基づくものが多くあてにならない。大学は20年前とは大きく変わっているのは言うまでもない。
まして50代、60代など年配になるほど、彼らからの大学の見方はあてにならない。30年前、40年前となればいまの大学とは別なのだから。
教育ジャーナリスト 小林哲夫:1960年神奈川県生まれ。教育ジャーナリスト、編集者。朝日新聞出版「大学ランキング」編集者(1994年~)、通信社出版局の契約社員を経て、1985年からフリーランスの記者、編集者。著書に『女子学生はどう闘ってきたのか』(サイゾー2020年)・『学校制服とは何か』(朝日新聞出版2020年)・『大学とオリンピック』(中央公論新社2020年)・『最新学校マップ』(河出書房新社2013年)・『高校紛争1969-1970 「闘争」の証言と歴史』(中公新書2012年)・『東大合格高校盛衰史』(光文社新書2009年)・『飛び入学』(日本経済新聞出版1999年)など。