大学・大学入試情報コラム
2026年度入試が動き出した。新課程の2年目だ。文科省からは、大学の新設予定、改組・学部の設置、募集人員の変更情報などが公表された。2026年度入試はどのように動くだろうか?

「定員割れ」学部はテコ入れが必要
2026年度入試は、「新課程入試」の2年目として実施される。各大学は今春の入試を総括し、早めに準備していた改組・新設学部情報などの変更点を盛り込み、2026年度用「大学案内」等の作成に取りかかっている。
4月9日には、文科省から「2026年度開設予定学部等認可申請一覧」等が公表された。収容定員の変更などを含めると、36校にも及ぶ。少子化等の影響で、私立大の2024年度の「定員割れ」が全体の59.2%を占めたため、改組・新設・定員変更などが増えた。志願者を増やすための、重要な方策なのだ。
文科省の推計によれば、大学進学者数は2026年度の63万人をピークにして減少に転じ、40年には45万人、50年には42万人にまで減少する。大学、特に私立大は「冬の時代」に突入することになる。
安易な学部・学科の新設は認めない
さらに、文科省は4月24日、私立大の学部新設時の審査基準を厳しくする方針を打ち出した。学生数が収容定員の「50%以下」の学部が1つでもあれば新設を認めない現在の基準を、「原則70%以下」まで引き上げる。少子化が加速する中、安易な学部・学科の新設を防ぐことが狙いで、2029年度の設置認可審査から適用される予定だ。
日本私立学校振興・共済事業団の私立大598校を対象にした2024年度の調査によれば、入学定員充足率が50%未満の大学は43校(7%)で、70%未満は113校(19%)だった。つまり、113私立大は学部の新設が認められず、経営的に厳しくなる。
この事態を予測した文科省は、在籍する学生が行き場を失わないように、早めの縮小や計画的な撤退を促すために、大学から事前に相談があった場合、弁護士や公認会計士らによる専門家チームを派遣し、資産の処分などの助言を行う。
また、文科省は経営が行き詰まった大学に撤退を勧告する際の目安も示す。学生の募集停止後、在学生が全員卒業するまでに必要な人件費や施設費が不足する場合を想定している。そして、経営難の大学への私学助成金の交付要件も厳格化する。
残念ながら、すでにこのような段階が想定される大学もあり、大学の倒産は遠い先の話ではない。「大学と名前が付くなら、どこでも構わない」なんて状況ではない。一方で、すでに2026年度入試は動き出しているのだ。
厳しい中でも私立大8校が新設予定
日々動く世界情勢や社会構造の変化、グローバル社会・IT社会・SDGs(持続可能な開発目標)への対応等で、新しい学びはどうしても必要になる。消滅する大学もあれば、誕生する大学もあり、文科省に2026年度開設予定大学の認可申請がなされている。
なかには構想中のケースもあり、変更もあり得る。また、名古屋柳城女子大・京都ノートルダム女子大は、2026年度以降の学生募集の停止を公表している。
| 【2026年度統合・新設予定の私立大学】 |
| [私立:統合] 学習院大:学習院女子大と統合(2026年4月統合) [私立:新設] 太田医療科学大(健康科学部:120人)、バリアフリー教養大(リベラルアーツ学部:225人)、コー・イノベーション大(共創学部:120人)、大阪医療大(医療看護学部:80人)、西日本看護医療大(看護学部:80人)、博多大(データサイエンス学部:160人)、福岡国際音楽大(音楽学部:80人)、武雄アジア大(東アジア地域共創学部:140人) |
理工系の学科統合や女子枠が目立つ
ここで、2026年度主要な大学の改組・新設学部などの動向を見てみよう。
国公立大では、山形大:地域教育文化学部→教育学部に改組、長野大:環境ツーリズム学部・企業情報学部→地域経営学部に再編、共創情報科学部を設置。佐賀大:コスメティックサイエンス学環、熊本大:共創学環、福井県立大:地域政策学部などを新設予定。
国公立大の特徴は、理工系を中心に学科の統合が目立つ。信州大:工学部(5→1学科)、九州工業大:工学部(6→1学科)・情報工学部(5→1学科)、兵庫県立大:工学部(3→1学科)など。また、理工系の学校推薦型や総合型選抜で「女子枠」の設置が相次ぐ。京都大:理学部・工学部、大阪大:基礎工学部、広島大:理学部・工学部・情報科学部など。人員は若干名が多い。
情報・データ・デジタル・デザインが多い
私立大では、すでに飽和状態でないかと思われるほどだが、情報・データ・デジタル・デザイン系の学部新設が続いている。特に、志願者減で苦境に立つ女子大では、男女共学、校名変更等に加えて、情報・データサイエンス系の学部新設が毎年続いている。
和洋女子大:AIライフデザイン学部、昭和女子大:総合情報学部、東京家政大:社会デザイン学部・文化デザイン学部、金城学院大:経営学部・デザイン工学部、京都橘大:デジタルメディア学部など。
この他では、中央大:理工学部→基礎理工学部・社会理工学部・先進理工学部、東京理科大:創域理工学部→創域情報学部、立命館大:デザイン・アート学部、桃山学院大:工学部など。
学環・学群は学部、学類は学科に相当
最近は、「学環」「学群」「学類」等の名称が目立つ。筑波大や金沢大に続き、佐賀大、酪農学園大など。一般的に学環・学群とは学部、学類とは学科相当の教育組織で、学群・学類制の方が、複数の分野を横断的に学び、学部・学科制よりも授業科目の幅が広い。
以前からある東京大:教養学部、京都大:人間総合学部、大阪大:人間科学部などのほか、多様な学問分野を自由に学び、各種のアプローチで問題の解決を図るリベラルアーツ学部と似たスタイルで、学際系学部、文理融合系学部などと称することが多いようだ。
大学&教育ウォッチャー 本間 猛:
東京理科大学理学部数学科1964年3月卒(参考 昭和39年:東京オリンピック・新潟地震)。元(株)旺文社取締役。中学・高校雑誌編集長,テスト部長,関西支社長等を歴任。
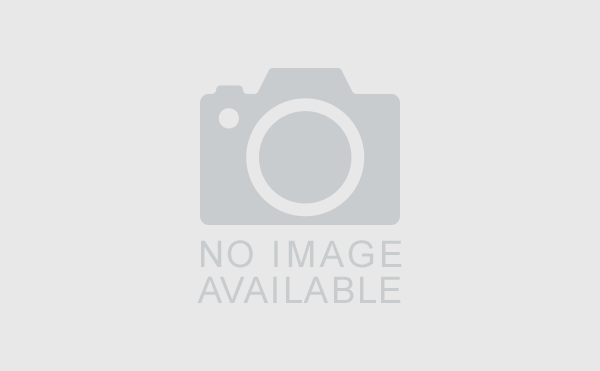
“” に対して1件のコメントがあります。