大学・大学入試情報コラム
新課程による2025年度「共通テスト」が実施され、平均点が対前年でアップした。新しい科目「情報Ⅰ」も、無難にスタート。2次・一般選抜に向けて、受験生が強気の出願をするか注目される。

新課程「共通テスト」は大きな混乱なし
新課程で初めての2025年度「大学入学共通テスト」は1月18日・19日に、全国651会場で実施され、大きな混乱はなく終了した。
大学入試センターによると、試験監督の指示ミス、電車の遅延、英語リスニング機器の不具合、さらに机への数学公式の書き込みなどの不正行為4件が確認され、4人が失格となった。なお、不正行為者は規定により、全科目の成績が無効となる。
また、同センターによれば、今回の「共通テスト」の志願者数49万5171人のうち、教科を受験した割合(受験率)は、地理歴史・公民80.8%、国語88.3%、外国語(リーディング・筆記)91.9%、英語(リスニング)91.3%、理科67.5%、数学①70.3%、数学②64.2%、情報61.0%だった。因みに、追・再試験は1月25日・26日、東京と大阪で実施され、対象者992人中希望者は54人だった。
対前年「平均点」アップで強気の出願?
2025年度「共通テスト」は、学習指導要領改定で、新教科「情報」を加え、出題教科・科目が6教科30科目から7教科21科目に再編。
基本的には、複数の資料を分析して思考力や判断力を測る出題であり、会話文形式、グラフや表等に基づく複数資料の考察などが求められる。受験生からは、「時間不足」の悲鳴が聞かされ、特徴の1つになっている。
入試センターが1月24日に公表した中間集計その2(受験者数45万1465人)の主要科目の平均点は、国語:(平均点:63.41点)、地理歴史・公民:地理総合・地理探究(57.55点)、歴史総合・日本史探究(57.06点)、歴史総合・世界史探究(66.20点)、公共・倫理(59.81点)、公共、政治・経済(62.74点)、数学:数学①数学Ⅰ・数学A(53.72点)、数学②数学Ⅱ・数学B・数学C(51.76点)、理科:物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎(60.10点)、物理(59.09点)、化学(45.46点)、生物(52.30点)、地学(41.69点)、外国語:英語リーディング(57.87点)、英語リスニング(61.44点)、情報:情報Ⅰ(69.46点)で、対前年でダウンしたのは地理、数学②、英語リスニングのみで、他はアップ。最終結果ではないが、アップ幅の方がダウン幅より大きく、「新課程導入年度は易しい」のジンクス通り、前年より易しかったようだ。2次では、強気の出願が予想される。
また、2025年度は得点調整対象科目の得点差が20点未満であり、今回は得点調整がなかった。因みに、共通テストの最終結果などは2月6日に公表される。以下に、「国語」と「英語」の特徴についてチェックしてみよう。
国語:「実用的文章」は試作問に類似
【変更点】多様な資質・能力を問うため、第3問「実用的な文章」を追加し、試験時間は10分増の90分。第1~3問の配点は、近代以降の文章で3問110点、古典が2問で90点(古文・漢文各45点)。「現代の国語」「言語文化」が必履修科目となった。
【問題分析】第1問:評論は、生徒の会話など複数のテキストがなく、シンプルな形式。
第2問:小説は、文章量が増加した。小説の設問数は前年と同じだが、答えるべきマーク数は減少。語彙に関する設問はなかった。
第3問:新規の「実用的な文章」は、外来語の言い換えについて取り上げられ、資料はグラフと文章の2つが出題された。(2022年試作問題Bに類似)複数テキストや言語活動の設問は第3問に集約した形になった。
第4問:鎌倉時代の物語と『源氏物語』の一場面からの出題。敬語の設問が課され、例年通り和歌の解釈も問われた。
第5問:江戸時代の漢学者の評論が取り上げられ、内容理解を軸とする出題だった。
【平均点】中間集計:国語は200点満点。
126.82点(63.41点)で、前年116.50点より10.32点(5.16点)アップした。
【難易】大問数・設問数は前年より増加したが、解答数は変更なし。大問全体を通じて、マークの標準的な数が5つから4つに減少したため、難易は「前年並み~やや易化」だった。
国語:SNSで「ヒス構文」が注目された
【話題】第2問の「もうわかった、あたしが死ねばいいんでしょ、じゃあ、死ぬよ」という一文で、「ヒス構文」が登場したと話題になった。「ヒス構文」とは、お笑い芸人のサーヤさんが動画で発信し、Z世代に話題になった言い回しのことで、「母が論理を飛躍させるなどしながらヒステリックな語気で相手に罪悪感を抱かせる構文」のことだ。
英語:全8大問になったが、易化傾向
【変更点】大問数が6問から8問に増えた。
【問題分析】《英語リーディング》:大問数は前年より2つ増加し、全8大問の構成。設問数は6つで、マーク数は5つ減少した。出題内容は、日常的な文章から説明文まで多岐にわたっていた。第3問と第4問以外のすべての大問で、図、表、イラストが使用されていた。
また第4問、第8問では新形式の出題があった。(2022年試作問題Bが第4問、Aが第8問に類似)試作問題は注視したい。
*語数:前年より約600語減少し、約5600語。
《英語リスニング》:前年と同じで、大問6題の構成。読みあげ回数は第1問・第2問が2回読み、第3問~第6問は1回読みだった。内容は、音声情報とイラストや図表などの視覚情報を組み合わせて答える出題が多かった。第5問は2022年試作問題と類似した形式。
*語数:設問および選択肢等の総語数は、前年とほぼ同じで約700語。
【平均点】《英語リーディング》:100点満点。
57.87点、前年51.54点より6.33点アップ。
《英語リスニング》:100点満点。61.44点、前年67.24点より5.8点ダウン。
【難易】《英語リーディング》:やや易化。
《英語リスニング》:前年並み。
情報Ⅰ:難易は標準で無難なスタート
新科目「情報Ⅰ」の試験時間は60分、配点は100点だったが、中間集計の平均点は69.46点と予想以上に高かった。
導入時には大学関係者の疑問の声もあったが、大問数4、設問数18、マーク数51で、情報Iの全範囲から幅広く出題された。難易は標準と言えそうだ。まずまずのスタートだった。
大学&教育ウォッチャー 本間 猛:
東京理科大学理学部数学科1964年3月卒(参考 昭和39年:東京オリンピック・新潟地震)。元(株)旺文社取締役。中学・高校雑誌編集長,テスト部長,関西支社長等を歴任。
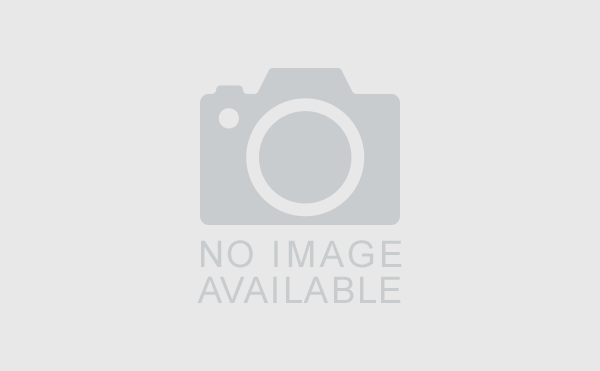
“” に対して1件のコメントがあります。